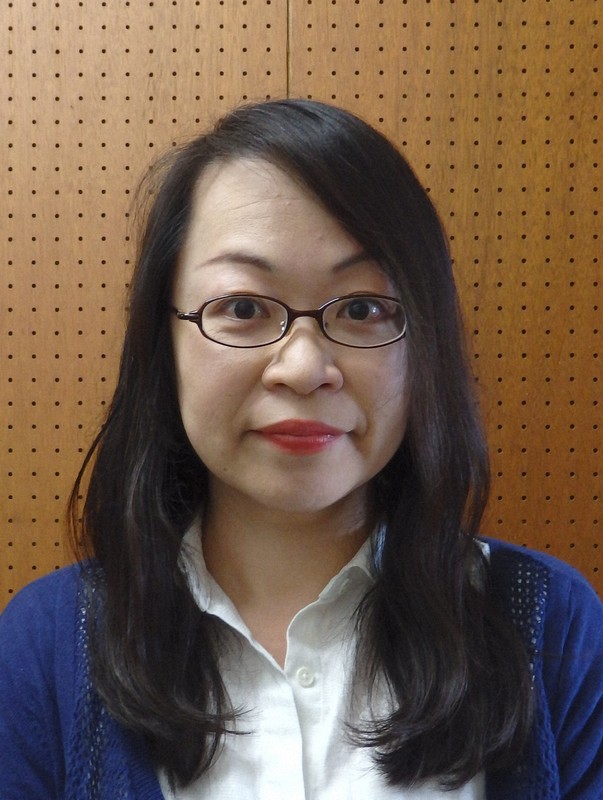
広島、長崎の原爆を体験した人々の言葉と生き様を記録し、後世に残すさまざまな努力が積み重ねられてきた。毎日新聞は2006年、記録報道「ヒバクシャ」の連載を大阪・西部本社発行紙面で開始し、300回を超えた。原爆投下から79年になろうとしている今、被爆者の肉声を報道し続ける意義について、広島大原爆放射線医科学研究所の久保田明子助教(アーカイブズ学)に聞いた。
被爆者の体験や人生を知りたければ証言集を読めば良いのかもしれない。被爆者の報道には、取材記者が介在することにより新たな情報を引き出してくれることに醍醐味(だいごみ)がある。
過酷な体験や苦難の人生を自分の息子や娘には話せないが、第三者である記者にならば赤裸々に明かせる人もいるだろう。プロのジャーナリストならばこそ、被爆者の気持ちをほぐすように心境を引き出せることもあるはずだ。
被爆の実相明らかに
かつては被爆者と明かすことが差別につながると恐れる人々がたくさんいた。高齢化して被爆者が減るにつれ、その体験は希少なものになっていく。被爆者として生きた歳月そのものが「生きる支え」になっている人もいるだろう。
「私」という像をどう語りたいのか。そう思っている被爆者が、自分の考えを引き出してくれる取材記者と出会い、お互いが同調しながら、被爆の実相を明らかにしていく。事実に基づいた上での「語り」が読み応えにつながる。それは被爆者が生きた「証し」であり、取材記者にとっても大切な財産だろう。
取材手法として、同じ被爆者から長い期間、定点観測のように話を聞くことで、時代ごとの「被爆者像」を写し取れているはずだ。年月を経るほどに被爆者と取材記者の年齢差は開いていくが、そこに若い記者ならではのみずみずしい感性がうかがえるときがあり、取材する側の人生がにじみ出ている記事もある。被爆者から大切なものを託されているのだろうし、試されているのだともいえる。
一つ一つの記事に付いている写真にも注目したい。取材と撮影の際にどんな視点で臨んだのか。記事とセットになっていることで印象を強めてくれる。
記事が学びの入り口に
新聞の力とは情報を伝えるだけではなく、創造性が大事だと思う。過去の原爆報道を振り返ると5年ごと、10年ごとの年に盛り上がり、23年の主要7カ国(G7)広島サミットのようなときに「特需」が起きる。
毎日新聞がつないできた長期連載の「ヒバクシャ」からは時代を捉え続けようという心意気が伝わる。貴重なアーカイブは、新聞社の「原爆報道史」ともいえる。記事の蓄積を活用しやすくすれば「原爆について学びたい」という人の入り口にもなる。
これからの大きな課題として、「被爆者なき時代」へのカウントダウンは既に始まっている。被爆者が語れなくなったとき、どんな話を報じるのか。それを考える際に忘れてはならないのは、表に出て話ができた被爆者は、ほんの一部に過ぎないことだ。語れなかった「語り」というものがある。
難しいテーマだが、報道の現場にいる記者だからこそ、それを引き出し、書いて残してほしい。それは被爆者と伴走してきた人々にとって、さらには後の世代への歴史的な資料となる。【聞き手・宇城昇】
くぼた・あきこ
1970年生まれ、東京都出身。高校の地理歴史科講師などを経て、2015年から広島大原爆放射線医科学研究所付属被ばく資料調査解析部の助教。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。





