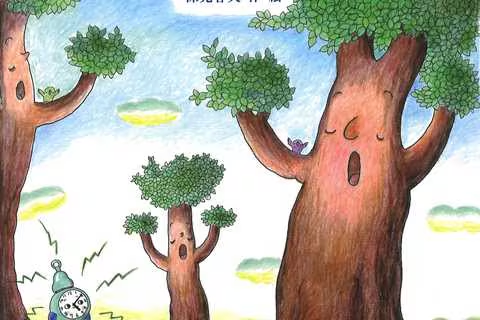『江藤淳はいかに「戦後」と闘ったのか』風元正著(中央公論新社・2750円)
昔々、文芸評論家が偉い時代があった。彼らは、文学だけでなく、世の中のあらゆることに意見を求められた。
というのも、文学が社会なり時代なりを深く穿(うが)っていたからだ。文学を足掛かりに、積極的に社会に向けて発言し、それが重要なものと傾聴された最後の世代と言っていい江藤淳が自ら命を絶ったのはそれゆえ世間を驚かせた。
まだ66歳で、戦後日本について言いたいこともまだたくさんあっただろう。本書もそこから書き起こされる。
ある程度時間軸に沿って語られるが、評伝ではなく、あくまで「戦後」と対峙(たいじ)する江藤の思想を解き明かすことに焦点が当てられる。
学生時代に書いた「夏目漱石論」が認められ、順風満帆な執筆活動を続けたと思われがちな江藤だが、長く書いたからこそ、そこには変化もあった。埴谷雄高ら左派の影響の下に出発した江藤がのちに保守派に転じたことは有名だが、その中にどのような思想の苦闘があったのか。
「奴隷」と「廃墟(はいきょ)」という2つのキーワードを通奏低音として、晩年までの江藤の思想を一貫して読み解く本書の手際は鮮やかだ。江藤の文芸評論と文明評論とを、点と点として読んできた者は、本書を通じてそれらが線で結びあわされて一気に全天の星座を成すのを体験するだろう。
とはいえ江藤賛美に傾くことなく、冷静にその言動を分析し、江藤が「戦後」の何とどう闘い、そして何故にあのような最期を迎えたのかが浮き彫りにされる。文学を通じて社会を変革しようとの試みは、文学そのものの変質によって不可能となったのだ。
戦後の言語空間を「閉ざされた」ものとして指弾した江藤だが、現在のキャンセルカルチャーのような形の言論弾圧は、江藤も知らない新たな閉塞(へいそく)を生み出している。アメリカの無意識の「奴隷」に甘んじつづけているわれわれは、ここでもまた輸入品の思想によって自らを閉ざそうとしている。江藤は草葉の陰からどう見ているだろうか。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。